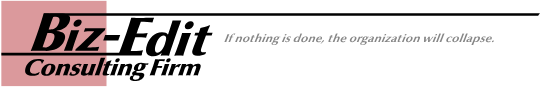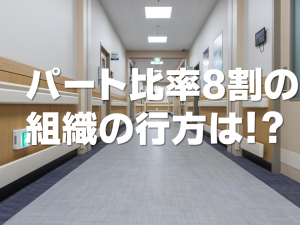『「事業」が先か「組織」が先か? ─社長の叫びから見えくる本質』
―売上は順調、でも人が定着しない。そんな声をよく聞きます。
ある中小企業の社長Aさんのハナシ。
「事業は順風満帆なのに、人を増やそうと50名採用したら、半年で20名が退社してしまった…。
働き方改革?労働時間?福利厚生?セクハラ・パワハラ研修?
ルールは一通り整えているはずなのに、原因がまったくわからない。
一体全体、どうしたらいいんだ!」
ハナシを聞いたとき、最初に思ったのは――
「従業員のための組織」になっていませんか?
多くの企業がハマる落とし穴。それは「従業員に快適さを提供すること」が組織づくりの本質だと勘違いしていること。
1.組織づくりの根幹は「事業を回すこと」にあり
組織はあくまで「事業・商売」を支えるための“部隊”です。
「人が幸せに働ける環境」を先に整えるのではなく、
儲けるための部隊をつくり、事業戦略を実現するために組織を設計する。
これが正しい順序。
採用:事業の成長ドライバーを担う人材を見極める
賃金:成果と役割に見合った報酬設計
能力開発・評価:事業課題を解決できるスキル育成と、公正な評価
これらを「一気通貫」で設計しないと、組織は事業と一体化せず機能しません。そして、社員のモチベーションは維持できず、定着率も上がらないのです。
2.順番を間違えると起こる「事業と組織の乖離」
事業戦略と組織戦略が分断現場ルールが“守るため”の仕組みに陥る
管理職が形骸化し、社長と現場のコミュニケーションが途絶
社員はただ“言われたことだけ”やるだけのアルバイト化
事業成果を出す個人だけが負荷をかぶり、離職が加速
――これが典型的な中小企業の負のスパイラルです。
3.では、具体的にどうすればいいのか?
ビジネスモデルと連動した組織図の策定
事業KPIと紐付いた人員配置と役割分担
成果を前提にした報酬・評価制度
現場の課題を拾う“管理職教育”と“現場指導”
数年先を見据えたキャリアパスと採用戦略
これらを統合的に設計・運用できるのが、いわば「組織コンサルティング」の醍醐味。
4.「儲ける組織」を実現するには第三者の視点が不可欠
社長や人事部だけで組織改革を進めるのは、どうしても社内バイアスに陥りがち。
経営と現場の“翻訳”
幼児性に陥った社員の動機づけ
管理職の役割浸透と育成
これらをスムーズに進めるには、善良でありながら“事業を理解する第三者”の存在が肝心です。
「組織の作り方」を知りたい方へ
事業をより高く伸ばし、社員が一丸となって成果を追いかける組織を設計したい――
そんな方はぜひ、下記よりお気軽にお問い合わせください。
組織と事業が一体となって回り始めたとき、会社の成長は飛躍的に加速します。