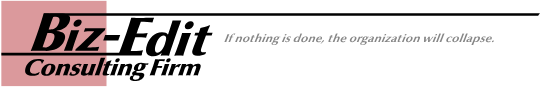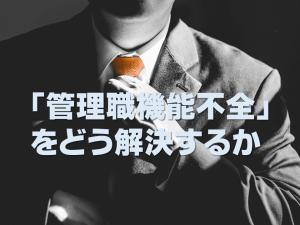社長がライオンになる理由と、No.2が作る組織
「うちの父親、なんでも自分で決めようとするんです。俺が何を言っても聞かないし…
まるでライオンですよ」
ある会社の後継者候補、社長の息子さんが、ぽつりと漏らした言葉です。
70代の創業社長。現場の声は届かず、全部自分でやろうとする。すべてを把握しないと気が済まない。
年齢からくる“頑迷さ”あるのかもしれないが、とにかく細大漏らさず報告を求める。
日本中の中小企業で見られる光景です。
でも、それって“あるある”! なんです。
「頑固で困る」って見えるかもしれないけど、それは社長の「責任感」と「不安」の裏返し。
事業をゼロから起こしたのならなおさら。“たたき上げ”という言葉が示す通り、
恵まれた環境や地位から出発したのではなく、現場での修行や経験を重ねて自力で上の立場や
成功を手に入れた人物ならではの言動です。
これまでの苦労を考えれば、社員の生活、資金繰り、銀行との交渉、顧客の信頼・・・。
どこから危機が襲いかかってくるかわからない。そのすべてを背負ってきた人にとって、
「任せる」という行為ほど難しいことはない。
「信じたいけど、任せきれない」
「楽をしたいけど、全部見ておきたい」
そんな葛藤のなかで、社長は一人、舵を握り続けているのです。
ライオン社長はなぜ怒るのか?
「なんでそんなことで怒るの?」
「そんな細かいこと、いちいち言わなくても…」
社内で怒鳴りまくる社長に、羊たる従業員は恐怖に打ち震えます。
でも実は、社長の“怒り”は単なる感情の爆発じゃありません。
あれは、「アラート」なんです。
・玄関が汚れている
・挨拶がない
・電話にすぐに出ない
・報告書があがってこない
・売上が下がっている・・・
社長はそれらに対して“違和感”を覚え、危機を感じています。
「このままじゃ危ない」という警告が、怒りという形で出ているんですね。
誰よりも会社のことを考え、常に360度アンテナを張っている。
そこに引っかかったシグナルに誰も気づかない。受け止めてもらえない。
だから、ますます声が大きくなる・・・。
「社長が孤独」とは、こういう背景があるわけです。
20人を超えたら、もう「個人商店」じゃいられない
創業当初や、従業員10人くらいまでなら、社長が業務の全てを見ることもできます。
しかしながら20人を超えると、会社は“組織”にならないと回らなくなってくる。
営業、製造、宣伝、採用、税務、そして最近ではIT、AIなどの最新技術・・・。
今までのように一人でこなせなくなるのは必然です。
そこで必要になるのが、「No.2と管理職」の存在です。
組織を作るのは、社長ひとりじゃありません。
No.2と各管理職が「現場と経営の間に立つ存在」として、体制を形にする必要があります。
このフェーズに入った会社では、No.2と管理職が“実質的なエンジン”になります。
No.2――参謀、右腕、あるいは黒子(くろご)。
表に立つわけでも、経営権を握るわけでもない。
でも、社長と社員の間でバランスを取り、現場の空気をつかみ、時に社長の思考の整理役にもなる。
歴史に名を残す企業にも、必ず「影の立役者」がいました。
SONYに盛田昭夫がいたように、読売巨人軍に牧野茂がいたように。
そういう存在がいる組織は二重の背骨があるような強固さがあります。
(令和の現代、めっきり聞かなくなりましたが・・・)
社長の「思い」を翻訳する
社長の言葉が言わず語らずで従業員に伝わる時代は終焉しました。
世代間で価値観は異なり、間を繋ぐはずの団塊ジュニアはピークアウト、
氷河期世代は採用薄で、技術やノウハウ、文化の伝承もままならない。
だからこそ必要なのが、「翻訳者」としてのNo.2と管理職。
社長が何に怒っているのか、何を大切にしているのか――
その“行間”を読み取り、現場が理解できる言葉に変換する。
そしてそれを実行可能な仕組みに落とし込み、現場が動く土台をつくる。
これができると、社長も社員もグッと楽になります。
組織に流れができて、会社の動きに一体感が生まれてくるわけです。
No.2に必要なのは、能力じゃない
それなら、No.2ってどんな人がなるべきなのか?
実は、「やたら頭が切れる人」「バリバリ営業できる人」よりも、
・黙々とやるべきことをやる人
・目立たなくても、周囲の信頼を集める人
・「誰かのために」が自然にできる人
そんなタイプの方が向いていることが多いんです。
(もちろん、社長の息子さんも最適任!)
何より大事なのは、「自分が表に出なくてもいい」と思えること。
それって、現代ではすごくレアで、でも、組織にとっては宝物みたいな存在です。
組織が息を吹き返す瞬間
No.2と管理職が現場に入ると、空気が変わります。
社員が「話を聞いてもらえた」と感じる。
社長が「任せられるかも」と思える。
そして、組織全体にじわっと広がる「安心感」。
その安心感こそが、人を育て、定着を生み、チームの推進力になります。
組織の駆動は、意外と「安心感」だったりするわけです。
従業員が委縮する組織は成果が期待できないのは自明の理です。
No.2の作り方
「自分の会社にも、そんな存在がいればなぁ」と思ったら。
あるいは、「自分がそのNo.2を目指せるかもしれない」と思ったら。
まずは、自社のなかに“もう一つの視点”があるかどうかを見直してみてください。
それが、新たな組織づくりの出発点です。
組織の作り方が分からない方、是非、お問い合わせください!