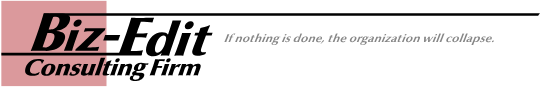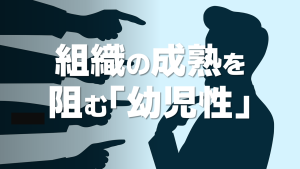社内の摩擦は動物タイプで見えてくる
オフィスはサファリパーク? 「キツネ型社員」が感じる職場の違和感
「どうして、あの人の話には納得できないんだろう?」
「なぜ、あんな曖昧な指示でみんな動けるの?」
「もっとロジカルに話してくれたら…」
こんなモヤモヤを抱えながら働いているあなた、もしかすると“キツネ型”かもしれません。
私は組織コンサルタントとして、これまで数多くの企業を見てきました。そして一つの事実に気づきました──人にはそれぞれ“思考と行動のクセ”があり、それは仕事のスタイルにも影響を与えているということです。
「キツネ」とは何者か? ソーシャルスタイル理論で見る“思考派”の特徴
産業心理学者のデビッド・メリルらが提唱する「ソーシャルスタイル理論」では、人の行動傾向を「ドライバー(行動派)」、「エクスプレッシブ(感覚派)」、「エミアブル(協調派)」、「アナリティカル(思考派)」の4つのタイプに分けて捉えます。その中で “アナリティカル型”には、以下のような傾向があります。
- 物事を論理的に考える
- 感情よりも事実を重視する
- 何かを決める前に、慎重に情報を集めて検討する
- 約束や決断に慎重で、確実性を重視する
- 「正しさ」や「納得感」にこだわる
これの特徴を動物に準えて、「キツネ型」と呼びます。キツネ型の人にとって「ちゃんと筋が通っているか」「なぜそれをやるのか」が非常に重要なのです。
「ノリと勢い」が苦手。キツネ型が職場で感じやすい“壁”
私自身も、この「キツネ」タイプに分類されます(汗)。かつて会社員だった頃、上司の“思い付き型”や“朝令暮改型”の言動に、何度も違和感を覚えた記憶があります。
「それって、ちゃんと考えた上での判断なの?」
「もっとシミュレーションしてから決めた方が良くない?」
でも、周囲はすでに走り出していて、私だけが立ち止まっていた。結果として、「慎重すぎる」「反応が遅い」と見られがちでした。
なぜ摩擦が生まれるのか?──キツネ型と職場の“ズレ”
キツネ型は、感情に訴えるリーダーシップや、雰囲気で動く組織にはなじみにくいことがあります。「正しさ」や「根拠」を重視するため、他のタイプとすれ違いが起こることも。
特に「曖昧な期待」「根拠なき楽観論」には強いストレスを感じやすく、「この人、本当に考えてるの?」と疑念を持つことすらあります。
しかし、これはキツネ型の“悪いクセ”ではありません。むしろ、組織にとっては非常に貴重な存在なのです。
キツネ型が活躍するには?──組織ができる工夫
キツネ型の人が力を発揮するのは、他のタイプの人がそれぞれの特性を理解することが必要です。「あの人は何型だっけ!?」 知っているのと知らないのでは大きな違いです。考え方や異なっても腹も立ちません。ならばこういうアプローチだな、と建設的な考えにシフトできます。
また、キツネ本人が周囲と良い関係を築くためには、「相手がどんな価値観で行動するのか?」考えることが大切です。感情で動く人や、直感を大事にする人の価値観を受け入れつつ、自分の強みを活かす。それがキツネ型の戦い方です。
まとめ:「キツネである自分」を誇っていい
論理を大切にし、納得感にこだわるキツネ型の人は、組織に“冷静さ”や“正しさ”という視点をもたらしてくれます。周囲とすれ違っても、自分の価値を見失わないでください。
そして、もし「キツネ型の部下」や「キツネ型の上司」がいたら、その人の視点にもう少し耳を傾けてみてください。そこには、組織の成長に必要なヒントが隠れているかもしれません。
組織コンサルティングで「ソーシャルスタイル」を取り入れたい方へ
本記事で紹介した「キツネ型」以外にも、職場にはさまざまなスタイルの人が存在します。当事務所では、こうしたスタイルを踏まえた研修・組織コンサルティングを提供しています。
「社員同士の理解を深めたい」「管理職育成に課題がある」と感じる方は、ぜひお気軽にご相談ください。