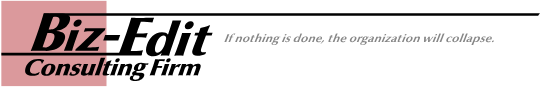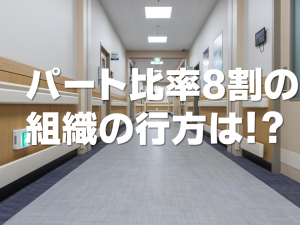形骸化した管理職の“あるある”と対策
「最近、若手が育たない」
「現場の雰囲気が何となく沈んでいる」
そんな相談を受けることが増えてきました。
社員数が20名を超えるあたりから、
組織には“目に見えない停滞”がじわじわと始まります。
これは“個人の能力”の問題ではありません。
“組織の構造と役割設計”の話です。
なぜか人が育たない組織に共通する 「見えない理由」
ある企業の支援で、現場の管理職からこう打ち明けられました。
「役職はついているけど、何をすればいいのかわからないんです」
話を聞くと、彼はもともとプレイヤーとして非常に優秀な社員でした。
しかし、マネジメントの訓練は受けておらず、
部下との接し方も評価の仕方も“我流”でやっているとのこと。
この話、実は決して珍しいものではありません。
・とりあえず古株をマネージャーに
・忙しすぎて部下育成の時間がない
・現場の混乱を“気合”で何とかしている
こうした状況は、表面的には機能しているように見えて、
実際には“組織が回っていない”サインです。
管理職の“自己流”が組織の限界を決めてしまう
多くの中小企業では、次のような問題が複合的に存在します。
・マネジメントの役割定義がされていない
・教育や研修の仕組みが存在しない
・上司自身が「見本」となる経験を持っていない
その結果どうなるか。
中間管理職は、部下を育てるどころか、自分も“プレイヤー”のまま。
やがて現場にはこうした空気が広がっていきます。
・部下が不安を抱えたまま放置される
・チームに活気がない
・評価や指示に納得感がない
・退職者が増えていく
これこそが、「なんとなく組織が停滞している」本当の原因です。
組織の正体は“リーダーの振る舞い”に現れる
若手社員にとって、会社とは社長ではなく「直属の上司」です。
その上司が信頼できるかどうかで、会社そのものの評価が決まります。
逆に言えば、管理職が機能し始めた途端に、
組織の雰囲気は劇的に変わり始めます。
・部下が安心して挑戦できるようになる
・指示が明確で、目標に納得感がある
・評価に基づいた対話ができる
・組織として“次のステージ”へ進める
つまり、会社を変える起点は「中間管理職の再定義」にあるのです。
「人が育たない」理由は明確だ
私たちは数多くの現場で、共通する“育たない理由”を見てきました。
・誰も仕事のやり方を教えてくれない
・誰も組織で働く作法を示してくれない
・誰も本物のリーダーを見せてくれない
こうした“教えてくれない文化”が、
人の成長を止め、組織の未来を奪っていきます。
でも逆に言えば、ここを変えることができれば、
どんな組織にも可能性はあるのです。
組織づくりは“統合的な設計”がすべて
採用・育成・評価・チームづくり──
これらをバラバラに対応しても、本質的な変化は起きません。
求められるのは、「戦略と組織を連動させた設計」です。
・リーダーの定義と役割の明確化
・チーム内でのコミュニケーション設計
・評価と目標管理の基準統一
・全体戦略と現場活動の“つながり”の創出
これらが整って、初めて人が育ち、組織が機能し始めます。
まとめ:変化の起点は、“中間管理職”にある
どれだけ優れた商品があっても、
どれだけ強い社長がいても、
組織が成長し続けるには、「リーダーが機能していること」が不可欠です。
そして、その起点となるのが中間管理職です。
だからこそ、 「なんとなくの管理職」から脱し、
「意志と設計を持ったマネジメント」へと進むこと。
それが、次のステージへ進む企業にとって、必要不可欠な一歩になるのです。
「うちも管理職がうまく機能していないかもしれない…」
そんな小さな違和感が、実は変革のチャンスかもしれません。
組織づくりや中間管理職の育成についてのご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。