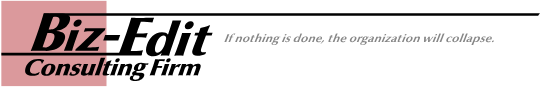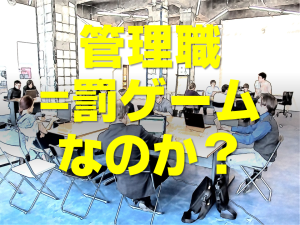「幼児性」が阻害する社員教育
隣の会話で感じた“違和感”
あるコワーキングスペースで聞こえてきた、新事業についてディスカッションについてです。詳しく聞こえたわけではありませんが、創業希望らしき50代女性の方は、スタッフの問いかけや提案に対し、少し食い気味に話を返してきました。「でもそれは…」「そんなふうには思っていませんでした」と、落ち着いた対話というより、どこか“応戦”のような応答でした。常に主導権を握ろうと、いや“会話の中心でいたい”というような、納得よりも自己防衛を優先しているように見えました。
空気がピリついたのは言うまでもなく、同席していたチームメンバーもどこか戸惑いの表情を浮かべていました。私はふと、「これぞ“幼児性”!」と感じたのです。
幼児性とは、“精神的に大人になりきれない”こと
この“幼児性”という言葉、近年、私の中で非常に重みを持って響いています。
それは単なる甘えやわがままとは違い、もっと根深い、精神的な未成熟さのこと。自分の思い通りにならないときに反発する。責任を持ちたがらず、周囲のせいにする。指摘されると過剰に反応し、自己を防衛する。変化を避ける。こうした姿勢は、誰かの“欠点”ではなく、成長のプロセスが止まっているサインかもしれません。
そしてそれは決して若手に限った話ではありません。私自身もそうですし、冒頭の女性にあったように、一定の年齢や地位に就いた中堅層や管理職の中にも、見えにくいかたちで潜んでいることが多いのです。特に不測の事態や窮地に追い込まれると顔を覗かせるやっかいな一面です。
昨今の政治やスポーツ界で話題になっている、組織のトップの煮え切らない態度も幼児性の一環ではないかと考えています。
日本総幼児化の要因
そもそも、なぜ今このように“幼児性”が目立つようになったのか──。
その背景には、日本社会があまりにも「豊かになりすぎた」という構造的要因があるのではないかと考えています。
かつて戦後の日本では、飢えや戦争、家族の生計を担うといった「生きるために大人にならざるを得ない」状況がありました。10代で弟妹の面倒を見て、家計を支える。ある意味では、“大人になることが強制されていた”時代です。
ところが現代は、物質的には満たされ、家庭も教育も安全が前提になった時代。
結果として、精神的に成熟する機会そのものが激減しました。
「やりたいことだけやっていればいい」「嫌なことは避けてもいい」といった風潮が、無意識のうちに“子どもでい続けても許される社会”をつくってしまったのかもしれません。まるで、社会全体で何でも他人のせいにする人間を製造する仕組みが機能しているように思えます。
この構造の変化は、若者だけでなく、すでに管理職や経営層になっている世代にも影響しています。だからこそ、現代の組織における人材課題の根底には、“社会全体の幼児化”という静かな流れがあるのだと、私は考えています。
教育が機能しない組織に共通する空気
ある種の組織では、幹部社員が「学び」を拒む文化をつくってしまっている場面に出会います。「今さら教えられたくない」「自分のスタイルを変えたくない」「これが正しいんだ」──そんな空気が、若手の育成の妨げとなり、結果として組織全体の成長を止めてしまう。
教育制度を導入しても、研修の設計を工夫しても、なぜか成果につながらない。そんなときに浮かび上がるのが、“教育を受ける側”の器の問題です。
つまり、「教育は、受け入れる土壌がなければ育たない」ということ。
その土壌を荒らしてしまう最大の要因こそ、“幼児性”です。
精神的自立を促すために必要なこと
では、どうすればこの幼児性を乗り越えられるのか。
私が現場で行っているアプローチの核には、単なる「知識の提供」ではなく、「人としての成熟を促す」ことにあります。たとえば、他者からの信頼を得ることの価値や、自分の役割が組織にどう影響しているかを実感してもらうこと。あるいは、安心して本音を話せる対話の場をつくること。こうした積み重ねが、徐々に精神的な自立を促していくのです。
よく、「自分らしく働きたい」という若手の声を耳にします。それは否定されるべきものではありません。ただし、その「自分らしさ」は、周囲との信頼関係や、一定の実績という“土台”の上にしか築けないものだと、私は考えています。
自由に自分らしく働くには、発言力が必要。
発言力には、信頼と成果が必要。
その順番を間違えないよう、導いていくことが教育の本質です。
管理職が学び直す文化が、育成の起点
そして忘れてはならないのが、管理職自身もまた「学ぶ存在」であるということ。
管理職が自己を省みず、「若手が育たない」とだけ嘆いていても、組織の風土は変わりません。上に立つ人ほど、自らの内面を見つめ直すことで、その姿勢が波紋のように広がっていきます。成長を止めないリーダーは、それだけで後輩にとって“生きた教科書”となるのです。
教育の質は、主体性で決まる
教育の質は、制度ではなくその人、その組織の主体性で決まる。
どれだけ立派な教育体制を整えても、受け手がそれを受け入れられなければ意味がありません。だからこそ、社員教育のスタート地点は“人を育てる前に、人が育つ状態を整えること”であるべきです。
私がご提供する組織コンサルティングは、まさにその“土台づくり”に焦点を当てています。人として成長する組織。精神的に成熟した関係性。安心して挑戦できる風土。
そこにこそ、社員教育の本当の価値が生まれると信じています。
「変わりたい」と思った瞬間がチャンス
「学ばない空気」を変えたい。
「育たない組織」を変えたい。
そう感じたときが、組織が変わる第一歩かもしれません。
中小企業の経営者、人事担当、管理職の皆さま。
変化を起こす準備が整ったなら、ぜひ一度ご相談ください。